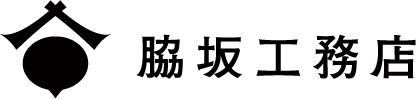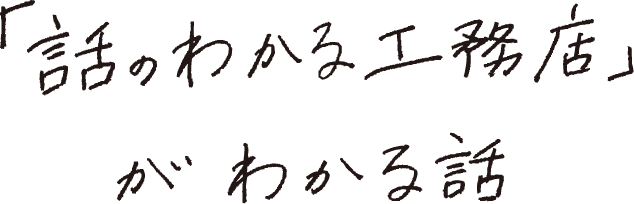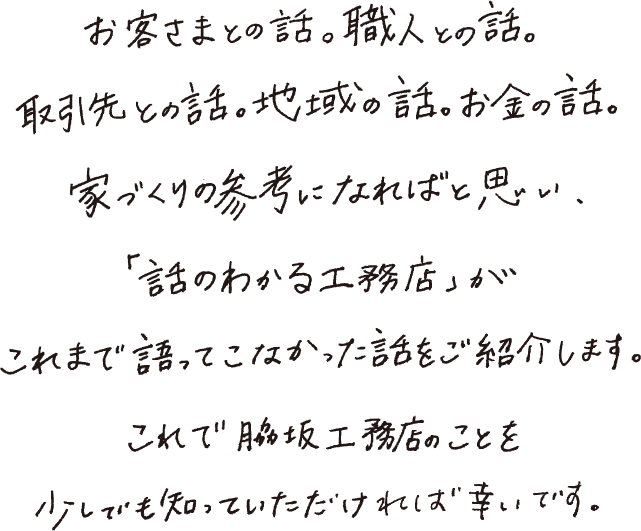
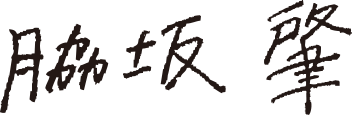
2025年4月18日 更新
#72
固定概念を壊せ。
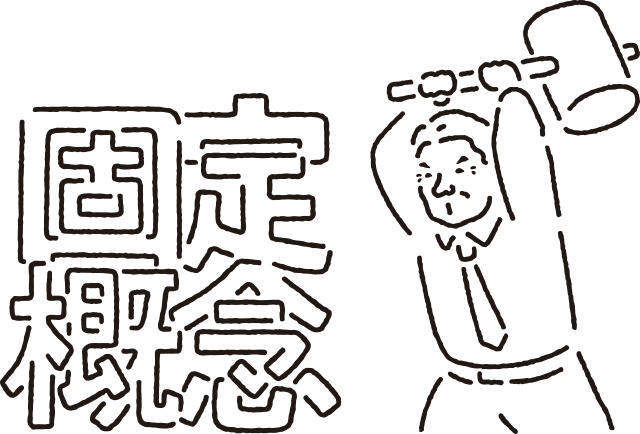
2025年3月末、脇坂工務店は、
31期目の決算を迎えようとしています。
これを執筆しているのは決算の直前。
営業事務がまとめてくれた数字によれば、
売上は前年度より下がっているものの、
不動産売買と仲介が好調だったおかげで、
利益は前年と同程度で着地しそうです。
31回目の決算か…。
私は62歳なので、
すなわち人生の半分を社長として
生きてきたことになります。
ただ…。
「社長」という役職にあまり自覚がないんです。
だって、社長って
ウケる話をする仕事ですよね…?
私の固定概念は壊れているようです。
中小企業の社長はある意味、何でも屋です。
自らあらゆることをやらないと、
会社がまわりません。
世間で思われるような、
「革張りの椅子にふんぞり返って、
口頭で指示だけ出す」
なんて事実は1ミリもなくて、
日々、大なり小なりの実務を抱えて
汗水垂らして働いております。
私と同様、
社長の実感が薄い中小企業経営者の方は、
多いんじゃないでしょうか。
社長と自覚するのは、
飲み屋の会計で
突然みんなが酔っ払ったフリをしはじめて、
「あれ、財布が見つからないな〜」
「見つからないな〜あれ?あれ?」
「あ、でも社長を見つけた〜」
「よっ!社長〜」
と言われる時くらいですね…。
私は社長じゃなくて財布なのでは。
社長の自覚がない他の原因としては、
うちの会社に役職がないことも考えられます。
一般的な会社組織であれば、
常務、専務、取締役、室長、部長、課長、係長etc.
といった役職がたくさんありますが、
当社はなし。
(便宜上、私は社長となっていますが)
最近の若い会社、
いわゆるスタートアップってところでは、
CEO(最高経営責任者)をはじめ、
CMO(最高マーケティング責任者)とか、
COO(最高執行責任者)とか、
CTO(最高技術責任者)とか、
横文字の役職が並んでいます。
あ、それで言うと私にも役職ありますね。
CEBです。
Chief Enkai Bucho
宴会部長です。
(正確には最高宴会部長)
こうやってCEBとか言っている人間なので、
「社長」と全然呼ばれないわけです。
「キミ、私を社長と呼びたまえ!」
みたいなタイプでもないですし。
また、うちの社員についてもみんな、
役職がないことを疑問に思っていない節があります。
社員同士は「〇〇さん」と呼び合うのが通例。
新入りの若者が最初「〇〇君」と呼ばれていても、
仕事ができるようになってメキメキと頭角を表し、
実力や経験が認められると、
いつの間にか「〇〇さん」と呼ばれていたりします。
役職にとらわれず、
お互いを認め合っている感じがして、
当社らしい自然なスタイルだと思いますね。
そもそも、実は、
私自身が役職ってヤツを嫌っているんです。
これまで肩書きを得たことによって、
人が変わってしまった例をたくさん見てきました。
それも悪くなる例ですね。
役職がついた途端に態度が大きくなって、
周りが協力しなくなり、自滅して失脚する…
みたいな人は結構いましたねぇ…。
権力にまつわる人の本能というか習性というか、
仕方ないのかな、とも思います。
権力は腐敗する、みたいな。
だから、「役職なんて必要ない」派なんです。
ただ、世間一般では
役職にこだわる人が多いのは事実。
会社員の話を聞いていると特に感じます。
役職があるから偉い、とか、人間的に優れている、
みたいな価値観が根強いのでしょう。
そういう凝り固まった概念、
固定概念ってものを
私は壊しがちなんですよねぇ…。
壊すというか「ぶっ壊し」がちなんです。
ぶっ壊すと言えば、
小●元首相が「自●党をぶっ壊す!」
と言ったり、
どこかの党首が「N●Kをぶっ壊す!」
と言ったりしています。
パクるわけではありませんが、
経営者として私の直近のスローガン、
テーマみたいなものを掲げるとしたら、
「固定概念をぶっ壊す!」
ということになります。
特に最近ぶっ壊したい固定概念があるんですよ…。
それは年齢です。
「高齢」とか「老後」とかの概念です。
何をもって「高い年齢」なのか?
何をもって「老いた後」なのか?
ってことです。
これはまさに固定概念じゃないでしょうか。
「高齢」とか「老後」とかいう概念が、
私にはないんです。
現在、脇坂工務店で活躍中の社員には、
65歳以上の人間が3名います。
年齢にとらわれない働き方を実践してくれています。
もちろん、個人差がありますし、
健康上の理由で思うように働けない方もいるのは
重々承知しております。
そういったやむを得ない事情の方は別として、
という前提で、
これからお話する内容をお読みいただければと。
最近、とりわけ「定年」という考え方に、
ハテナマークがつくんです。
私自身が62歳という年齢だからかもしれません。
60歳とか65歳といった年齢で
どうして一斉に線を引いて辞めさせるんだろう、と。
人がたくさんいる時代であれば、
上の世代が多すぎてつっかえているから、
組織の「新陳代謝」を促す仕組みとして導入された、
とかならわかります。
若者の活躍を促していく必要がありますからね。
あと、退職金をたくさん払えるだけの体力が
会社にあるなら、
そういう仕組みを導入しても問題ないでしょう。
でも、今や日本は少子高齢化に伴う悩みが
噴出しまくっています。
人口統計を見ていても、
これからその課題が
急激に解決される可能性は極めて低い。
人材が足りないわけです。
かたや、年齢を重ねてはいるものの、
働く意欲があって、
実際に実力や経験を持っている人はいます。
そんな状況下で、
定年というルールっているのかな?
と思うんです。
サッカーに例えると、
オーバーエイジ枠がめちゃめちゃあるわけだから、
フル活用したほうが、ビジネスという試合で
勝てる確率が上がるんじゃないか、
って思うんですよね。
当社に在籍しているオーバー65トリオ。
全員バリバリですよ。
1人は70歳の現場監督。
体力、あるんですよね。
私なんかよりも全然。
ある時、私が気を使って、
「もうちょっと気楽に働けるよう、
仕事の量を減らして時給制にしますか?」
って提案したことがあるのですが
「このままでいいっす!」
と却下されました。
本人としては別にペースを落として、
のんびり働きたいとは思わないのだとか。
確かに何ら問題ないどころか、
貴重な戦力として大活躍してくれているので、
このままフル稼働してもらえるなら、
それはそれで会社として大変ありがたいわけです。
残り2人はどちらも65歳で、
不動産事業の担当をしてもらっている人材。
不動産業って経験や知識がモノを言う仕事ですが、
私が何を聞いても、法的なことを含めて、
すぐに答えを返してくれる頼もしい存在です。
今回の決算が好調だったのは
不動産事業のおかげですし、
当社になくてはならない戦力となっています。
しかし、一般的な会社だったら、
彼らはもう定年の年。
再雇用制度みたいなものがある会社は増えましたが、
あくまであれは特例として、ですよね。
給料とか下がるパターンが多いようですし。
「こんなにうちの会社で活躍してくれているのに、
他社では定年になってしまうって、どうなの…」
とちょっとモヤモヤしております。
先日、
当社のオーバー65トリオとは正反対な人たちを、
たまたまYouTubeで目にしました。
年金受給者に街角でインタビューする企画です。
話をしている方は、みんな仕事を辞めており、
「年金が足りない」
「これだけでは暮らしていけない」
と口を揃えていました。
“優雅で悠々自適な老後”なんて人は
一人もいません。
(もちろん動画制作側の意図が
多分に含まれての人選でしょうけど)
ただ、気になったのは
みんな不満を言っていることです。
そんな人たちを見ると、私はつい、
「もし体が大丈夫であれば、
定年後も働けるように準備をしておくべきでは…」
と思ってしまうんです。
日本の社会情勢を見ていれば、
老後がどういう状況になるのか、
火を見るよりも明らかだったわけですから。
つまり、年金だけで優雅に暮らせない可能性が高い、
ということは、かなり前からわかっていたはず。
それ相応の準備ができたんじゃないかって
思うんですよね。
もし仮に年金がない国とか時代に生きていたら…
と想像してみましょう。
狩りとか農耕とかが主の時代であれば、
定年なんて悠長なことは言ってられないでしょう。
「お前、何言ってんだよ!
目の前に鹿が走っているから捕まえろ!
じゃないと、今晩のごはんがないぞ!」
ってなりそうです。
繰り返しになりますが、
個々人の事情によるので、
私の考えだけが正しい!とは
口が裂けても言いません。
ただ。
心身ともに健康である限りは、
年齢に関係なく、社会に求められて
働き続けるのがいいんじゃないか。
それが私の意見です。
短時間でもいいから、
常に社会とつながりを持っていることって大事です。
人の幸福度は財産の多さとかではなく、
人とのつながりの多さ、豊かさで決まる。
そんな研究成果を何かの記事で読みました。
お金をいくら持っていても、
誰ともつながりを持っていない、
薄い人間関係しかなかったら、
そりゃあ味気ない人生になりそうです。
誰かに必要とされているうちが花ですよ、ホント。
例えば、
「60歳になったから、あなたの好きな沖縄で
老後暮らすのに、
一生困らないだけのお金をあげます。
家も用意します」
みたいな制度を、
仮に会社が用意してくれるとしても、
人とのつながりがない場所だったら、
たぶん1ヶ月で飽きるんじゃないですかね…。
私だって、ある日道端で神様に会って、
「毎日サザンのライブ行っていいよ!
お金も使い切れないくらいあげます。
でも、働いちゃダメ」
って言われたら、最初のうちは、
「イエーイ!」
ってなるでしょうけど、
たぶん3日目のアンコールあたりで、
「もう無理です…働かせてください…」
って号泣している気がします。
趣味とか旅行とかって、
忙しい合間を縫っていくから楽しいんですよねぇ。
特に私と同世代や先輩の皆さん、
「定年」みたいな
型通りのルールに縛られることなく、
働けるうちはもっと働きましょうよ。
つまり、何が言いたいのかというと…
現在、脇坂工務店では現場監督を募集しています!
ということです。
さも、社会に物申す的な雰囲気を
醸し出しておきながら、
これは求人案内だったのです…!
詳しくはこちらの求人情報を どうぞ。
(リンク先の募集が終了している場合もあります)
ポイントは年齢制限がない募集ということ。
ここまでお話してきた内容からすると当然ですね。
他社でよくあるような、
「一定の年齢を超えたら給与をカットします」
みたいなことも、うちはしていないですし。
当社の現在の仕事状況を踏まえると、
あと2、3人現場監督がいても全然仕事があります。
相変わらず各種プロジェクトが立て込んでいて、
例えば、
倶知安ニセコエリアで進行中なのが、
某世界的建築家のプロジェクト。
完成したら、どえらいことになりそうです。
なんじゃこりゃ〜!みたいな建築です。
前述のオーバー65歳トリオ以外にも
2024年に入社した59歳の現場監督がいるんですが、
60歳を迎えた現在も、
最前線でバリバリ働いてくれています。
年齢が高い人を採用して、
活躍してもらっている実績が
いくつも当社にはありますのでご安心ください。
AIの台頭が著しいですが、
現場監督って、
いまだに人間じゃないとできない仕事。
現場をスムーズにまわすために、
ちょっとした気配りをする、
なんてこと、人じゃないとできませんから。
まだまだ現場監督のニーズはあると思っていますよ。
この歳になって、しみじみ思うのは、
自分の能力や経験を発揮できる場があるのは、
幸せだなぁってことです。
私の場合は、営業の能力や、
ラジオでの話し手としての経験、
不動産ビジネスの知識などなど、
いまだにお客さまや取引先、仕事仲間たちから
必要とされているから、
こうして会社を続けていられるわけです。
ありがたいことです。
これを読んでいるベテラン現場監督の方にとって、
当社がそういう仕事の機会を提供できればと
願っております。
マジです。
60歳を「終わった人」とか、
65歳を「高齢者」と呼ぶような
固定概念を一緒にぶっ壊しませんか。
昔つくられたルールに縛られるなんて、
おかしいじゃないですか。
私たちは、まだまだこれからですよ!
…と勢いよく、ここまで書いてきましたが、
今、この文章を読んだ社内スタッフから
指摘が入りました。
「『固定概念』は辞書に載っていない言葉です」
え?
「『固定観念』と同じ意味で使う人が多いんですが、
いわゆる誤用ですね」
え…。
も、もちろん知っていますよ…。
「固定概念」の使い方の固定概念も壊したいと
私は思っていますから、
と、当然知ってますとも…。
あ、いや、正確には、
「固定概念」の使い方の固定観念…?
ああ、わからない!
私の脳が定年を迎える前に、
現場監督の方、力を貸してください…。
脇坂肇